
冬場になると口の端が切れてピリピリと痛む、食事のときにしみて痛い……。
あなたはそんな体験ありませんか?
ずっと口を閉じているわけにもいかないので、なかなか治りづらいのがこの口角炎(こうかくえん)ですネ。
では、どのような予防や対策があるのか紹介していきますネ。
スポンサーリンク
目次
口角炎とは?
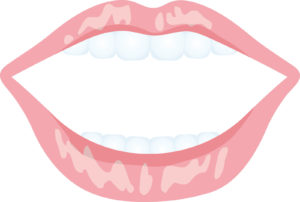
口角炎(こうかくえん)とは、唇の両端である口角が炎症を起こし、赤みや腫れが生じる皮膚炎のことです。
口角のほかにも、くちびるに症状が出る場合は口唇炎(こうしんえん)といいます。
乾燥する冬の時期や、体調を崩したときにあらわれやすく、赤みや腫れのほかにも、出血や亀裂が入るなどの症状が出ます。
|
|
口角炎の原因
口角炎になる原因はいろいろとありますが、こちらのような原因が主なものです。
・カンジダ菌
・ビタミンB群の不足
・乾燥
・体調不良(胃の不調、ストレス)
そのほかにも、刺激物を食べたり、癖で口の端をなめる、指で触ってしまうといった場合にも起こるんです。
カンジダ菌
カンジダ菌はカビの一種ではありますが、健康な状態でも身体にいる常在菌です。
口や腸内にも住んでいますが、身体の免疫力が落ちるとその数が増え、病気の症状を引き起こします。
口角炎に似た症状
そのほか、口角炎に似た症状として口唇ヘルペスがありますが、口唇ヘルペスはヘルペスウイルスが原因であり、口への違和感やかゆみのあと、口角炎とは違い水ぶくれができる点が特徴です。
口角炎の予防と対策

口角炎自体は重い病気ではありませんが、口元にできる病気のため、食事をしたり話したりなど日常の動作一つに影響してきますネ。
では、どのような予防と対策があるのか紹介しますネ。
口角を刺激しない
口角炎は刺激により発症することも多いため、前述しています口の端をなめたり、指で触るといったことは控えるようにしましょう。
タオルやふきんで口をこすり過ぎないことも予防になります。
保湿をする

肌のバリア機能が落ちていると、少しの刺激で口角炎になりやすくなります。
乾燥が気になるときは、ワセリンなど刺激の少ない保湿剤を使って保湿をしましょう。
口角炎は保湿することを忘れずに体調を整えれば、自然と治ることも多くあります。
なので、保湿も心がけましょう。
体調管理をしっかりする
免疫力の低下が原因の一つとなるため、ストレスや疲労をためないこと、睡眠不足に気を付けることが大切です。
免疫力が上がれば予防にもなるほか治りも早くなります。
ビタミンB群を摂取する
ビタミンB群は皮膚や粘膜の健康状態を維持する役割もあります。
そのためビタミン不足になると、口角炎にもつながってしまいます。
ビタミンB群は肉類や野菜などそれぞれにまんべんなく含まれているため、偏った食事にならないよう、肉類と野菜をバランス良く摂るようにしましょう。
肉類や野菜だけでなくビタミンB群は、実は甘酒にも含まれています。

米麹(こめこうじ)で作る甘酒も、酒粕(さけかす)で作る甘酒も両方ビタミンB群が含まれています。
甘酒は“飲む点滴”と言われているほど、栄養価が高い飲み物ですネ。
⇨甘酒の効能と熱中症※知らない主婦は損するかも知れない豆知識まとめ!
米麹で作られた甘酒は、アルコールが含まれていません。
スポンサーリンク
医師に診てもらう

悪化する場合はその時点で早めにお医者さんに相談するようにしましょう。
自己判断は逆に症状を長引かせることもありますので、皮膚科や口腔外科を受診することがおすすめです。
口角炎は物理的な刺激でもできやすいですが、まずは体調を整え免疫力を落とさないことが大切です。
他の病気が原因かも?
ほかの病気が原因で口角炎があらわれることもありますので、なかなか治らないということがある場合は、早めにお医者さんに相談するようにしてくださいネ。
私の場合の口角炎対策

私がやっている口角炎対策を紹介しておきますネ。
とっても簡単な方法なので、効果には個人差があると思いますがお試しくださいネ。
『重曹を溶かした水でうがいをする!』これだけなんです。
重曹の量ですが、コップ一杯の水に対して、小さじ山盛りぐらいを入れてください。
なめてみてちょっと塩辛いぐらいがいいと思います。
口の端の切れているところには、重曹を溶かしたその液を指で塗ってくださいネ。
でも、残念ながら、口の端が切れて跡が残ってしまっているのは、手遅れなので治りません。
スポンサーリンク
まとめ
口角炎の予防と対策は、口角を刺激しない、保湿をする、体調管理をしっかりする、ビタミンB群を摂取する、保湿する、医師に診てもらう、重曹を溶かした水でうがいをしたり切れているところに塗るなど。
ここまでお読みいただきありがとうございます。



コメントは受け付けていません。